視聴覚教材を検索
教材が決まりましたら、お電話ください。
TEL 092-947-3514
視聴覚教材 検索結果詳細
検索一覧へ戻る| 分類番号 | D17021H |
|---|---|
| 表紙画像 |
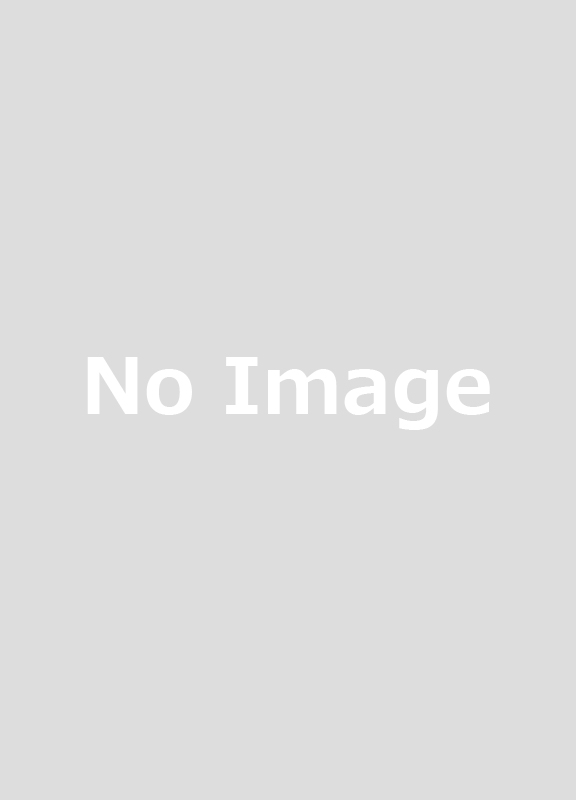
|
| 題名 | 「稲むらの火」の物語~津波防災教材~4作品収録(日本語版) |
| 対象 | 小学校,中学校,成人 |
| 分類 | 国語,地震,防災(その他),アニメーション |
| 上映時間 | 72分 |
| 媒体 | DVD |
| 教材内容 |
「稲むらの火」は、昭和初期から戦前にかけて、小学国語読本に掲載された物語です。 「稲むら」とは、収穫され束ねられた「いなわら」のことです。津波到来に気づいた村の賢者(庄屋)が村人を避難させるために村の高台の「稲むら」に火を放ち、村人を救うお話です。津波災害の怖さ、日頃の信頼の大切さ、機転の大切さを小中学生に感じとってほしいと願う作品です。 主人公の浜口梧陵は、百年後に再来するであろう津波に備え、巨額の私財を投じて、海岸に高さ約5m、長さ約600mの広村堤防(防波堤)を築き、その海側に大量の松を山から移植し強固なものにしました。 そして安政南部地震から92年後の昭和21年、昭和の南海地震が発生し、高さ4~5mの大津波が広村を襲いましたが、 梧陵が築いた広村堤防は、村の居住地区の大部分を津波から守ったのです。 ●デジタル紙芝居(14分) ●人形劇(30分) ●影絵劇(18分) ●戦前版・紙芝居(10分) ●解説 |
