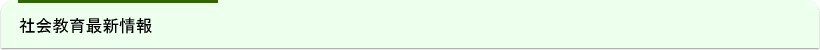| 回 |
年 |
フォーラムのテーマ |
事例数 |
| 42 |
令和7年
  |
特別報告
口演「教育が社会を変える~今こそ意識改革~」
特別企画
「青少年教育の原点と『未来の必要』~今、改めて問い直す社会教育の役割~」
| 1部 |
「家庭教育調査結果にみる保護者の実態と社会教育の役割
~40年間で何が変わったのか、何が必要なのか、何ができるのか~」 |
| 2部 |
「子どもを核にした人づくり・地域づくりと社会教育の底力
~地域が子どもを育む!益田市の挑戦~」 |
|
24 |
| 41 |
令和6年
 |
特別報告
「妻の定年~家庭内男女共同参画の最終章~」遺稿を読み解く
特別企画
「三浦清一郎が問い続けた『未来の必要』~その教育思想と実践~」
| 1部 |
「各地生涯教育実践研究交流会の展開と意義
~大会はなぜ広がったのか、何をもたらしたのか~」 |
| 2部 |
「青少年教育の原点と学社連携の可能性
~タフな子どもを育てる教育プログラムと支援の仕組みを問う~」 |
|
24 |
| 40 |
令和5年
 |
特別報告
「幼老共生の社会教育戦略」
愛知県扶桑町の市民聴講制度と福岡県飯塚市の熟年者マナビ塾
~義務教育学校の市民解放~
特別企画
| 1部 |
「教育こそ未来より先に動かなければならない」 |
| 2部 |
「生涯教育実践研究交流会 40年を振り返って」 |
|
28 |
| 39 |
令和4年
 ※ ※
令和2・3年度
延期 |
特別報告
「気を抜かず、『前期』楽せず、がんばれば、健康寿命は『後期』までもつ
-後期高齢者の健康原則-」
特別企画 〈インタビュー・ダイアローグ>
『大学・企業』と繋がる社会教育の「未来の必要」
~地域づくり・人づくりへの役割~
| 1部 |
「生涯教育と企業の連携はいかにして生まれ、社会教育の未来をどう変えるか?~宮崎モデルの可能性~」 |
| 2部 |
「大学と自治体が始めた『地域連携協定』は、両者に何を生み、どう変えるのか?」 |
|
24 |
| 38 |
令和元年
 |
特別報告
「グローバル時代の日本文化再考」 ~文化がつくりだす「国柄」と「副作用」~
特別企画 〈インタビュー・ダイアローグ>
「超高齢社会の『未来の必要』」
| 1部 |
「高齢社会の放送大学」~その使命と活用の可能性~ |
| 2部 |
「『学習療法』で認知症高齢者の脳機能活性化に挑む」 |
|
28 |
| 37 |
平成30年
 |
特別報告
老いてひとりを生き抜く -暮らしに負けず、自分に負けず、世間に負けず-
特別企画〈インタビュー・ダイアローグ〉
「男女共同参画時代の子どもの発達支援」
| 1部 |
「保教育」を展望する「飯塚プラン」の革新性 |
| 2部 |
「通学合宿」の30年を振り返る |
|
28 |
| 36 |
平成29年
 |
特別報告
不登校・ひきこもりの根本問題 -分析と対処法が間違っていないか?-
特別企画〈特別講演〉
「未来の日本人を鍛える」
| 1部 |
ヨコミネ式保育の理念と方法、子どもの可能性を引き出す
-成果・普及・未来展望-ヨコミネ式保育は何を目指し、何を成し遂げたのか |
| 2部 |
なぜ「尾道100キロ」か-「若い力を若い力が育てる」プロセス-
次世代育成思想・企画・運営・成果を検証する |
|
28 |
| 35 |
平成28年
 |
特別報告
現行施策では地方創世はできません -国土の均衡発展:その原理と方法
-「消滅自治体」を救うのは、小中学校の地方分散事業である-
特別企画
| 1部 |
「小中学校聴講制度」の先見性と未来性
-予算の要らない「生涯教育」、「世代間交流」、「教室の覚醒」、「高齢者の脳トレ」- |
| 2部 |
「生涯教育実践研究交流会」の意義と使命
-「仕掛人」に聞く組織化の手順・方法・成果と実態- |
|
28 |
| 34 |
平成27年
 |
特別報告
「国際結婚の社会学-国際化で日本文化は変わるか?-」
特別企画(インタビュー・ダイアローグ&「笑学校」の教育実習)
「笑学校」の理論と実践
| 1部 |
「笑い」の中にどう「教育的メッセージ」を織り込んで行くのか? |
| 2部 |
「笑い」の中で何を言えというのか? 注文の多い二人の晩学者に聞く |
| 3部 |
(1)「笑学校」の教育実習 |
| |
(2)矢野大和校長の講評…「笑い」+「教育的メッセージ」 |
|
28 |
| 33 |
平成26年
 |
特別報告
「心の危機」を予防する
-医者に見えない教育問題、教育者が気付いていない医学症状-
特別企画(2つのミニ講演とインタビュー・ダイアローグ)
「発想を変える、ボーダーを超える」
1 若者支援のフロンティアに挑む
2 過疎地の教育振興に挑む
3 インタビュー・ダイアローグ
二つの実践の哲学・原理・方法論を聞く |
28 |
| 32 |
平成25年
 |
特別報告
「健康寿命を延ばす」-暮らしの老年学の原理と方法-
特別企画(インタビュー・ダイアローグ)
1部 ~幼児期の教育プログラムについて~
「『鍛える』幼稚園・保育園に問う。-今なぜ幼児鍛錬なのか?-」
2部 ~高齢者の社会参画を考える~
「高齢研究者に問う。2020年の『高齢者爆発』をどう回避すべきか?」 |
28 |
| 31 |
平成24年
 |
特別報告
「人は2度死ぬ-自分史は『紙の墓標』」
特別企画(インタビュー・ダイアローグ)
1部 「通学合宿等『生活体験プログラム』の意義と方法
2部 「壊れた地域社会を修復し、『無縁社会』を突破する方法はあるか?」 |
28 |
| 30 |
平成23年
 |
第30回記念大会
特別報告
「30年:741事例の教訓」
特別企画(インタビュー・ダイアローグ)
未来の必要~「学習」から「教育」へ~ |
28 |
| 29 |
平成22年
 |
特別報告
「生涯現役の方法~「生きがい」の構造~」
特別企画(リレーインタビュー・ダイアローグ)
第1部 女子商『企業市場』は高校生の何を変えたか?
第2部 学童保育になぜ教育プログラムが不可欠なのか?
第3部 区政に市民参画は何をもたらしたのか?
第4部 相談事業はなぜ社会復帰に成功しないのか? |
28 |
| 28 |
平成21年
 |
特別報告
「変わってしまった女、変わりたくない男」(男女共同参画の現状)」
特別企画(インタビュー・ダイアローグ)
第1部 小学校教育の革新-現在進行形
第2部 生涯現役の方法-日々の実践と精進 |
28 |
| 27 |
平成20年
 |
特別報告
「保小連携の教訓~『生きる力』の基礎と土台の欠損」 ~総括とインタビュー~
特別企画(インタビュー・ダイアローグ)
第1部 「子ども政策の総合化」 ~分野横断型の子育て支援~
第2部 「少老共生」 ~学社連携に向って学校が動く~ |
28 |
| 26 |
平成19年
 |
特別報告
少子高齢化対策は停滞し、「教育公害」がやってくる
特別企画(インタビュー・ダイアローグ)
第1部 『地域との連携による学校の改革と
学校との連携によるコミュニティの形成』
-「連携の条件」と「相互貢献の条件」-
第2部 『NPOの創意と挑戦に学ぶ』 |
28 |
| 25 |
平成18年
 |
特別企画(インタビュー・ダイアローグ)
第1部 『それぞれの「定年と老い」の準備プログラムと展望』
「何をしたいのか?なぜなのか?できるのか?」
第2部 『残された「生涯時間20年」時代の生涯学習施策を問う』 |
28 |
| 24 |
平成17年
 |
特別企画(インタビュー・ダイアローグ)
第1部 テーマ:その後の学力向上戦略(第2回討論)
「学力」とはなにか?「学力向上の方法」はなにか?
「学力は向上しているのか?」
第2部 テーマ:「子育て支援」サミット
誰が、なんのために、何を、どのようにやるのか? |
28 |
| 23 |
平成16年
 |
特別企画(インタビュー・ダイアローグ)
第1部 テーマ:学力向上の戦略を問う
「学力」とはなにか?
「学力向上の方法」はなにか?
「学力は向上しているのか?」
第2部 テーマ:「なぜ落語と口演か?」
「落語と口演による生涯学習理念と方法のプレゼンテーション」
落語と口演2題:1年400回「口演」のエッセンス |
28 |
| 22 |
平成15年
 |
特別企画 生涯学習における未来事業開発のためのインタビュー・ダイアローグ
テーマ1「完全学校週5日制と土曜教育力」
テーマ2「男女共同参画」
テーマ3「生涯学習のためのNPO活動」 |
28 |
| 21 |
平成14年
 |
学社融合の可能性:「総合的な学習」の中身と方法を問う
~「生きる力」になり得る体験とは何か?総合的学習で「学力」は大丈夫か?~ |
28 |
| 20 |
平成13年
 |
第20回記念大会 企画リレートーク
21世紀の生涯学習施策の展望 |
28 |
| 19 |
平成12年
 |
特別企画 シンポジウム
生涯学習の推進と出前講座 |
32 |
| 18 |
平成11年
 |
特別企画 シンポジウム
健康と生涯学習 |
32 |
| 17 |
平成10年
 |
特別企画 シンポジウム
生涯学習社会における学社融合 |
32 |
| 16 |
平成9年
 |
特別企画 シンポジウム
生涯学習社会における高齢者の社会参加 |
32 |
| 15 |
平成8年
 |
シンポジウム
コミュニティの創造と企業の参画 |
32 |
| 14 |
平成7年
 |
シンポジウム
日本の社会は「いじめ」の論理に耐え得るのか |
32 |
| 13 |
平成6年
 |
シンポジウム
生涯学習とボランティア |
30 |
| 12 |
平成5年
 |
シンポジウム
環境と生涯学習 |
32 |
| 11 |
平成4年
 |
特別企画(緊急シンポジウム)
6日目の子どもたち ~学校5日制への対応~ |
32 |
| 10 |
平成3年
 |
特別企画
高齢化社会の生涯学習
10周年記念事業
生涯学習とコミュニティ戦略 ~九州市町村インタビューダイアログ~
各市町村での実践 ~生涯学習をどうコミュニティ形成にいかすか~ |
19 |
| 9 |
平成2年
 |
特別企画
「ふるさと創生」事業におけるまちづくりの視点と課題 |
31 |
| 8 |
平成元年
 |
特別企画
県レベルにおける生涯学習推進システムづくりと具体的取り組み
~九州2県の模索・検討の歩みから~ |
33 |
| 7 |
昭和63年
 |
特別企画 シンポジウム
地域における国際交流事業の企画と展開
~九州地区の実践と成果に学ぶ~ |
32 |
| 6 |
昭和62年
 |
特別企画
市町村における生涯教育推進のための連携方策の研究~「昭和61年~」
~「昭和61年度福岡県市町村生涯教育事業調査」報告と提案~ |
33 |
| 5 |
昭和61年
 |
5周年特別記念事業
生涯学習時代の企業内教育 |
21 |
| 4 |
昭和60年
 |
なし |
23 |
| 3 |
昭和59年
 |
会場:福岡県立社会教育総合センター、以下40回大会まで同じ会場 |
14 |
| 2 |
昭和58年
 |
会場:福岡教育大学 |
13 |
| 1 |
昭和57年
 |
会場:福岡教育大学 |
6 |